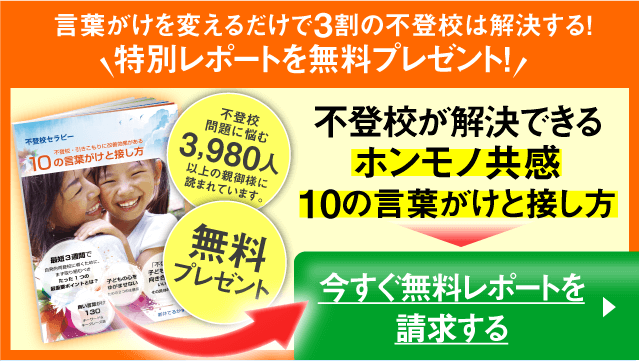この春の進級・進学シーズンは、私が長期で開催している魔法ことば講座を受講してくれた方から、嬉しい報告が毎日のようにきていますので一部をご紹介します。
「昨日は娘の卒業式でした!
私は参加できなかったのですが、おしゃれをして先生や友達と記念写真を撮ったり、友人たちと春休みの遊びのプランをたてたりととても楽しそうでした。
また、将来はインターナショナルな仕事に就きたいとのことで、先生とも相談をして進学先も決めました。
4月からはJ大学で英語とフランス語を学びます。
数年前は、こんな日が来るとは想像することもできませんでした。
不登校カウンセリングと、新井先生はじめ川嶋トレーナーには本当に感謝です。 改めてお礼申し上げます。」
「息子が、週1回のクラブ活動に、テニスラケットとシューズを買って、参加するようになりました。
毎回筋肉痛だ!と言っていますが、息子の話しぶりなら楽しんで活動出来ている様子が伝わってきます。
先月初め後期試験がありました。数日前から試験対策をして取り組んでいました。
試験当日も時間に余裕を持って、母の送迎ではありましたが、学校に向かう事ができました。
前期試験では大事なのは理解しているけれどそれから逃げ出してしまいたい気持ちと戦っていましたが、今回の試験ではそんな様子は1mmも感じられず落ち着いていて、驚きました。
まだまだ車で学校への送迎がある日々であった1月末、定期券を買って欲しいと本人から言われて購入しました。学校に車で送迎を頼まれる事もありますが、定期券を購入後は基本的には電車で通学しています。
前を向いてしっかりとした足取りで歩いていく背中に、頼もしさと安心を感じました。
それだけ母の私に不安が強かったのだと思います。
初めて電車で通学した日の息子の様子はちょっと不安気な表情に、背中をすくませて下を向き、歩幅も短く歩いて駅に向かう姿であり、とても頑張っているんだなぁと感じさせるものがありました。
ここ数日は制服で電車通学をしています。制服を来て電車に乗る事をあんな頑なに嫌がっていたのに、ただただ驚きと、制服姿の息子を駅で見送る日がくるなんて嬉しい気持ちです。」
「娘が、2月に結婚しました。家族みんなで幸せに包まれました。本当に嬉しいです。
お相手はなんと、、小学校の先生をしている同い年の人です。
娘は、新しい仕事にチャレンジで遠くの会社に勤めました。しかし予想とは違って変わり者集団だったとわかり、ものすごくまだ苦労してしまいました。
しかし、共感力からだんだんと仲間が増え、2年近く勤めましたが自力で辞めることができました。
そんな中、出会った人に支えられ、そして結婚にまで至りました。
私も,最初にあった時から大賛成のお相手です。
あんなに苦労したのに,学校の先生と?と,私たちはちょっと笑ってしまいましたが、娘が心を許せるそして,尊重し合える人に出会えて本当に良かったです。」
「今年の春、息子は無事志望の大学に受かりました。
高校は1年生の夏に転校して通信の学校に行き始めました。
はじめはぼちぼち登校の様子でしたが、高校2年の半ばくらいから週5日間通うようになり、「やはり学校は毎日いかなければいけないと思う」などと言いはじめました。
学習面では、ほぼ4年間も全く勉強していませんでしたので、高校3年生で合格した大学は志望大学ではありませんでした。
受かったことに満足してそのままその大学にいくのかなとも思いましたが、本人から「もう1年やらせてほしい」との発言があり、自分から浪人することを選択しました。
長いブランクがありますので、予備校では習得する教科を限定しての勉強になりました。
親としては、金銭的な面からも国立にいってほしい、私立ならば最高峰に、、、などと欲がでてしまうところでしたが、そういうときは新井先生のブログをみて新井先生のご尊顔を拝し、気を引き締め、本人のやりたいように見守ることができました。
うちはありがたいことに、父親のハンドリングがとても上手で、夫にも感謝感謝の日々でした。
結果、志望校を含めうけた大学はほぼ全部合格しました。最高峰ではないけれど難関私大と言われているところもほぼ全部です。
ただ、現在本人は人より科目を多くやっていないことを後ろ向きにとらえ、これからが大変だと感じている気持ちがひしひしと伝わってきています。
自分は勉強をしていないから、一般常識を何もしらないと。。。
不安なこともたくさん口にしていますが、これから彼がどのように選択していくのか引き続き見守り続けたいと思います。
とにかく大学受験までこぎつけた今の段階でご報告をさせていただきたいと思い連絡をさせていただきました。
これからの方が大変でしょうが、ちょこっとの成長が心にしみるこの頃でした。」
こんなふうに嬉しい報告が続出しています。
なぜ、子供にこんなふうに劇的な変化が起こるのか?
その理由はたった1つです。
親御様が私の講座でしっかりとホンモノ共感を身につけたからです。
不登校の原因は、実は子供の劣等感です。
子供は劣等感で自己肯定感を下げてしまい、そんな自分を隠すかのように不登校になってしまっています。
この劣等感を改善し、子供の自己肯定感を高めるのがホンモノ共感なのです。
ホンモノ共感とは子供の情緒、気持ちに寄り添い、共感していくことです。
特に子供がネガティブな状態で、悩んだり、不安になったり、怒ったりしているときに、その状態をそのまま受け止め、そう感じている子供の気持ちに寄り添い、共感していくことがとても重要です。
なぜなら、そういうときにこそ、共感されないと、「こんな自分はダメだ。」と劣等感を感じてしまうからです。
親御様が子供がネガティブな状態のときに、ホンモノ共感できるようになると、「こんな自分でも大丈夫なんだ。」と安心感を子供は感じていきます。
この安心感が親子の愛着関係の土台となり、自己肯定感を高めていくことができるのです。
そして、結婚した娘さんのように、子供が親御様からのホンモノ共感を体験することができると、子供自身も他人にホンモノ共感できるようになります。
すると子供がつらい人間関係の場に入ったとしても、共感によって、人間関係を改善して、自分らしくいることができるぐらいの高い自己肯定感と自信をもつことができるようになるのです。
こんなふうにあなたも親子で幸せな人生を手に入れませんか?
とはいっても、ほとんどの親御様はホンモノ共感を自分の親からしてもらったことがありません。
そのためいくら言葉で説明したとしても、実際にホンモノ共感を体験しない限り、ぴんとこないことがほとんどですし、本当の意味で子供にホンモノ共感することはできません。
ですので、不登校を解決するホンモノ共感を実際に体験できる、魔法の言葉がけセミナーを3-4月にも開催することにしました。
セミナーでは不登校の真の原因とともに、どのように不登校を解決していくのかについての詳しいプロセスについても、お伝えします。
また最短2週間で再登校を実現したホンモノ共感の言葉がけの実例についても、特別にお教えしますので、以下から魔法の言葉がけセミナーの詳細を確認の上、ご参加くださいね。
↓↓↓
【魔法の言葉がけセミナー&説明会】
<開催日程>
自宅から受講できるウェブ会議 ズーム(ZOOM)で開催
- 2025/3/20(木祝)13:00-17:30
- 2025/4/11(金)13:00-17:30
- 2025/4/12(土)13:00-17:30
ホンモノ共感クイズ「夫婦間の会話」
前回のホンモノ共感クイズには、4名の方から回答いただきました。ありがとうございます。
どの方の回答もとてもいいと思います。
もし私がこのお母さんの立場なら、穏やかに「今、話しがすり替わっちゃったよ。」とやわらかく伝えます。そしてなるべく固有名詞はあまり出さず、いくつものヒット曲というような言い方にするだろうと思います。
このお父さんはもちろん悪意は全くありません。それどころか何とか自分を変えようと意識してくださっています。
ただどうしても、アピールが出やすいですので、おそらくお父さんには劣等感があるのでしょう。
お父さんの劣等感に真正面から取り組むか、それを避けるかは、どちらが正解かということないと思います。
ちなみに私はこのお父さんの劣等感にカウンセリングで直接、切り込んでいく予定にしています。
助かるのはお父さん自身が以下の癖に気づき、なおさねばならないと思ってくださっているところです。
・自分がアピールをしてしまう癖があること
・お母さんの話をすり替える癖をあること
・ついつい知識量でお母さんに劣る部分を何か別の話でつなげようとする癖があること
お父さんはお父さんでカウンセリングを受けて、なおすとして、お母さんももちろん悪気はないものの、無自覚にお父さんの劣等感を刺激するような会話になっているというところに着目して、知識や情報ではない、情緒的な会話を可能なかぎり心がけていただきたいところです。
ホンモノ共感クイズ「自分の母親への共感」
あなたはご自身の母と同居しているとします。あなたも母親も料理が好きで、料理番組をよく一緒に見ますが、あなたの母は少々、口が悪いところがあります。
ある料理番組をみているとき、「この料理まずそうね。」と母親が言い出しました。
その場には他の家族もいたので、「これは共感すべきかどうなのか?」とあなたはかなり迷いました。
この場合、もし母親にホンモノ共感するとしたら、どんな言葉がいいでしょうか?
あなたが考えるホンモノ共感の言葉がけを3/24(月)14:00までにブログにコメントください。
来週3/26(水)のブログで私が考えるホンモノ共感の言葉がけをお伝えしますので、この機会を活用して、不登校の改善に役立ててくださいね。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。